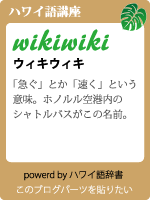2016年10月22日
今帰仁村湧川の路次楽
 祭りでは、この区に伝わる「路次楽(ろじがく)」や独特の棒術も披露され、同区外からもカメラを手に会場を訪れる人の姿もありました
祭りでは、この区に伝わる「路次楽(ろじがく)」や独特の棒術も披露され、同区外からもカメラを手に会場を訪れる人の姿もありました この方たち、私にこの踊りは何?とか、今やっているのは何の意味があるの?とか聞いてくるのですが、私も正直言って初めて見物したので分からないことだらけ・・・
この方たち、私にこの踊りは何?とか、今やっているのは何の意味があるの?とか聞いてくるのですが、私も正直言って初めて見物したので分からないことだらけ・・・ ちょこっと調べてみました
ちょこっと調べてみました
路次楽は元来中国のもので、琉球王国の中国伝来の宮廷音楽。それが今から約480年前の16世紀、尚真王時代(1522年)明国の世宗皇帝即位慶賀使として、中国入りした澤岻親方盛里(たくしうぇーかたもりさと)が皇帝の行列で路次楽の吹奏を見聞し、その勇壮華麗さに感動し、楽器とともに演奏法を習いおぼえて沖縄に持ち帰ったといわれています。楽器も独特で、哨ナ(ツォナ)、笛、銅角(ウシブラ)、ウマブラ、大鼓、小鼓、両班(リャンハン)、銅鑼で奏でられます。路地楽は首里城での儀式などで演奏されたもので、現在でも首里城の古式行列などで観ることができます。
湧川には、今から約200年前に與儀家先祖、與儀銀太郎が湧川に住み、哨吶(つおな)の音楽を初めて村芝居に採り入れ、村人達にも教え広めるようになったそうです。
湧川の路次楽で使用する吹奏楽器「ガク」や「獅子」は、戦時中、壕の中で大事に保管され、完全な姿で残り、今に至っているといいます。路次楽の芸能については、子孫である與儀家が哨吶の楽器制作方法や奏法などを代々受けついでいます。路地楽の音楽は中国では明時代に滅びましたが、沖縄では400年以上も現存していることは大変貴重ですね。


(こちらの2枚の写真はお借りしました↑)
豊年祭に奉納される踊りは、大体どこも同じ演目が並ぶと思いますが、湧川区では少々珍しいものがありました
 豊年祭で最初に演技をする場所、メンピヤーと呼ばれています
豊年祭で最初に演技をする場所、メンピヤーと呼ばれています ここで棒術、路次楽、が奉納され、次に獅子小屋の庭へ道じゅねーで移動
ここで棒術、路次楽、が奉納され、次に獅子小屋の庭へ道じゅねーで移動

そこで長者の大主・二才踊り・女踊り・ドラ・路次楽・棒術のメンバーが集い、路地楽や棒術や踊りが演じられ、獅子舞も登場します
 寝ている獅子を起こし、獅子小屋の外へ出します
寝ている獅子を起こし、獅子小屋の外へ出します これは、獅子ワクヤー(獅子使い)の役目で、踊りながら少しずつ外へ誘導するのですが、その子の踊りがすごく上手で感動しました
これは、獅子ワクヤー(獅子使い)の役目で、踊りながら少しずつ外へ誘導するのですが、その子の踊りがすごく上手で感動しました 路次楽の吹奏楽器「ガク」の音は、チャルメラのCMで流れているような笛の音にすごく似ています
路次楽の吹奏楽器「ガク」の音は、チャルメラのCMで流れているような笛の音にすごく似ています 独特の雰囲気に包まれます
独特の雰囲気に包まれます そのあと、公民館野外ステージ前で棒術が奉納され、豊年祭の踊りが舞台ではじまります
そのあと、公民館野外ステージ前で棒術が奉納され、豊年祭の踊りが舞台ではじまります 最後の演目は「七福神」を紹介する歌にあわせて七福神が舞います
最後の演目は「七福神」を紹介する歌にあわせて七福神が舞います 初めて拝見しました
初めて拝見しました すべての演目が終わると、再び獅子屋の前で、棒術の奉納
すべての演目が終わると、再び獅子屋の前で、棒術の奉納 それから獅子をまた小屋に帰してウートートー
それから獅子をまた小屋に帰してウートートー これですべて終了です
これですべて終了です すごーく長い豊年祭でしたが楽しく見ました
すごーく長い豊年祭でしたが楽しく見ました ありがとうございました
ありがとうございました
Posted by aromama at 09:50│Comments(0)
│その他