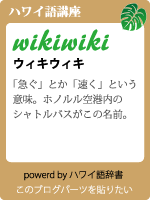2016年07月18日
浜比嘉島
6月の中旬に浜比嘉島へ行ってきました~ 梅雨はとっくに明け、夏本番
梅雨はとっくに明け、夏本番 あちぃ~
あちぃ~ 海の駅「あやはし館」から見る砂浜
海の駅「あやはし館」から見る砂浜 左が平安座島、右奥が浜比嘉島
左が平安座島、右奥が浜比嘉島 息子たちは、すぐに下りて行ってしまいます~
息子たちは、すぐに下りて行ってしまいます~

まず向かったのが、地頭代火ぬ神(じとうでーひぬかん)

旅の安全、立身出世の神様を祀っています 沖縄の一般家庭の台所には「火ぬ神(ひぬかん)」を祀り、火の神様を崇める風習があります
沖縄の一般家庭の台所には「火ぬ神(ひぬかん)」を祀り、火の神様を崇める風習があります 浜比嘉島の「地頭代火ぬ神」には、神が宿るよう3個の霊石を祀っています
浜比嘉島の「地頭代火ぬ神」には、神が宿るよう3個の霊石を祀っています 琉球王府時代、浜集落には地頭代の役地があり、地頭代になるためにはその前に浜地頭に就いて役割を果たさなければならなかったそうです
琉球王府時代、浜集落には地頭代の役地があり、地頭代になるためにはその前に浜地頭に就いて役割を果たさなければならなかったそうです 火の神が奉納されたのは、このころだったと言われています
火の神が奉納されたのは、このころだったと言われています 旅に出るときは必ずここで祈りを捧げていたため、現在も旅立ちの際にはお祈りする習わしがあり、立身出世、進学の神様としても有名です
旅に出るときは必ずここで祈りを捧げていたため、現在も旅立ちの際にはお祈りする習わしがあり、立身出世、進学の神様としても有名です もちろん、息子達の立身出世をお願いしましたよ
もちろん、息子達の立身出世をお願いしましたよ
次は、アマミチュー


海に出っ張ったアマンジと呼ばれる岩の小島があります 琉球開びゃくの祖神二人が眠る島で、コンクリートの道が作られていて、渡ることができます
琉球開びゃくの祖神二人が眠る島で、コンクリートの道が作られていて、渡ることができます 小島にある小さな階段を登ると洞穴に守られるようにしてお墓があり、これが、琉球開びゃくの祖神・アマミキヨ(アマミチュー)とシネリキヨ(シルミチュー)のお墓といわれています
小島にある小さな階段を登ると洞穴に守られるようにしてお墓があり、これが、琉球開びゃくの祖神・アマミキヨ(アマミチュー)とシネリキヨ(シルミチュー)のお墓といわれています 旧暦の1月1日に行われる年頭拝み(ニントゥウグワン)という祭事で女司祭にあたる比嘉集落のノロ(祝女)が五穀豊穣、無病息災、子孫繁栄の祈願を行います
旧暦の1月1日に行われる年頭拝み(ニントゥウグワン)という祭事で女司祭にあたる比嘉集落のノロ(祝女)が五穀豊穣、無病息災、子孫繁栄の祈願を行います
続いて、シルミチュー霊場

琉球開びゃくの祖神シネリキヨ(シルミチュー)とアマミキヨ(アマミチュー)が生活し、子どもをもうけたところと伝えられ、年頭拝み(ニントウゥグワン)にはノロ(祝女)が海浜から小石をひとつ拾い、洞窟に安置されている壺に入れて祈願しています 洞窟内には鍾乳石の陰石があり、子宝が授かる聖域としても有名
洞窟内には鍾乳石の陰石があり、子宝が授かる聖域としても有名
車を比嘉湾港内にある駐車場に停め、細いあぜ道を少し進むと鳥居がみえます そこをくぐり、うっそうと生い茂る木々のなか百段余りある階段を登ると、入り口に柵がされた鍾乳洞があり、拝所になっています
そこをくぐり、うっそうと生い茂る木々のなか百段余りある階段を登ると、入り口に柵がされた鍾乳洞があり、拝所になっています
シルミチュー霊場のすぐ目の前にある天然の兼久ビーチ あまりの暑さに子供たちは入っちゃいました~
あまりの暑さに子供たちは入っちゃいました~

最後に、シヌグ堂

ガジュマルの大木に守られた祈りの場 浜比嘉島では、旧暦の6月28日と8月28日に海が時化(しけ)ることを祈る「シヌグ祭り」が行われることから「シヌグ堂」と呼ばれる御嶽があります
浜比嘉島では、旧暦の6月28日と8月28日に海が時化(しけ)ることを祈る「シヌグ祭り」が行われることから「シヌグ堂」と呼ばれる御嶽があります 東(あがり)の御嶽とも言うそうです
東(あがり)の御嶽とも言うそうです 海が時化ることを祈るとは不思議な祭りだが、その昔、三山時代、戦いに敗れた南山の「平良忠臣」とその陣営が海を渡り、ここに身を隠したという謂われがあり、敵陣が海を渡れないように時化を祈ったことから始まっているそうです
海が時化ることを祈るとは不思議な祭りだが、その昔、三山時代、戦いに敗れた南山の「平良忠臣」とその陣営が海を渡り、ここに身を隠したという謂われがあり、敵陣が海を渡れないように時化を祈ったことから始まっているそうです 神々しい大きなガジュマルと祠があり、近くには自然石を利用した井泉「ハマガー」や、右手側にある階段を約10メートル登ると拝所もありました
神々しい大きなガジュマルと祠があり、近くには自然石を利用した井泉「ハマガー」や、右手側にある階段を約10メートル登ると拝所もありました
浜比嘉島、とても静かで穏やかな時間が流れている場所です 楽しかったです~
楽しかったです~
 梅雨はとっくに明け、夏本番
梅雨はとっくに明け、夏本番 あちぃ~
あちぃ~ 海の駅「あやはし館」から見る砂浜
海の駅「あやはし館」から見る砂浜 左が平安座島、右奥が浜比嘉島
左が平安座島、右奥が浜比嘉島 息子たちは、すぐに下りて行ってしまいます~
息子たちは、すぐに下りて行ってしまいます~
まず向かったのが、地頭代火ぬ神(じとうでーひぬかん)


旅の安全、立身出世の神様を祀っています
 沖縄の一般家庭の台所には「火ぬ神(ひぬかん)」を祀り、火の神様を崇める風習があります
沖縄の一般家庭の台所には「火ぬ神(ひぬかん)」を祀り、火の神様を崇める風習があります 浜比嘉島の「地頭代火ぬ神」には、神が宿るよう3個の霊石を祀っています
浜比嘉島の「地頭代火ぬ神」には、神が宿るよう3個の霊石を祀っています 琉球王府時代、浜集落には地頭代の役地があり、地頭代になるためにはその前に浜地頭に就いて役割を果たさなければならなかったそうです
琉球王府時代、浜集落には地頭代の役地があり、地頭代になるためにはその前に浜地頭に就いて役割を果たさなければならなかったそうです 火の神が奉納されたのは、このころだったと言われています
火の神が奉納されたのは、このころだったと言われています 旅に出るときは必ずここで祈りを捧げていたため、現在も旅立ちの際にはお祈りする習わしがあり、立身出世、進学の神様としても有名です
旅に出るときは必ずここで祈りを捧げていたため、現在も旅立ちの際にはお祈りする習わしがあり、立身出世、進学の神様としても有名です もちろん、息子達の立身出世をお願いしましたよ
もちろん、息子達の立身出世をお願いしましたよ
次は、アマミチュー


海に出っ張ったアマンジと呼ばれる岩の小島があります
 琉球開びゃくの祖神二人が眠る島で、コンクリートの道が作られていて、渡ることができます
琉球開びゃくの祖神二人が眠る島で、コンクリートの道が作られていて、渡ることができます 小島にある小さな階段を登ると洞穴に守られるようにしてお墓があり、これが、琉球開びゃくの祖神・アマミキヨ(アマミチュー)とシネリキヨ(シルミチュー)のお墓といわれています
小島にある小さな階段を登ると洞穴に守られるようにしてお墓があり、これが、琉球開びゃくの祖神・アマミキヨ(アマミチュー)とシネリキヨ(シルミチュー)のお墓といわれています 旧暦の1月1日に行われる年頭拝み(ニントゥウグワン)という祭事で女司祭にあたる比嘉集落のノロ(祝女)が五穀豊穣、無病息災、子孫繁栄の祈願を行います
旧暦の1月1日に行われる年頭拝み(ニントゥウグワン)という祭事で女司祭にあたる比嘉集落のノロ(祝女)が五穀豊穣、無病息災、子孫繁栄の祈願を行います
続いて、シルミチュー霊場


琉球開びゃくの祖神シネリキヨ(シルミチュー)とアマミキヨ(アマミチュー)が生活し、子どもをもうけたところと伝えられ、年頭拝み(ニントウゥグワン)にはノロ(祝女)が海浜から小石をひとつ拾い、洞窟に安置されている壺に入れて祈願しています
 洞窟内には鍾乳石の陰石があり、子宝が授かる聖域としても有名
洞窟内には鍾乳石の陰石があり、子宝が授かる聖域としても有名
車を比嘉湾港内にある駐車場に停め、細いあぜ道を少し進むと鳥居がみえます
 そこをくぐり、うっそうと生い茂る木々のなか百段余りある階段を登ると、入り口に柵がされた鍾乳洞があり、拝所になっています
そこをくぐり、うっそうと生い茂る木々のなか百段余りある階段を登ると、入り口に柵がされた鍾乳洞があり、拝所になっています
シルミチュー霊場のすぐ目の前にある天然の兼久ビーチ
 あまりの暑さに子供たちは入っちゃいました~
あまりの暑さに子供たちは入っちゃいました~
最後に、シヌグ堂
ガジュマルの大木に守られた祈りの場
 浜比嘉島では、旧暦の6月28日と8月28日に海が時化(しけ)ることを祈る「シヌグ祭り」が行われることから「シヌグ堂」と呼ばれる御嶽があります
浜比嘉島では、旧暦の6月28日と8月28日に海が時化(しけ)ることを祈る「シヌグ祭り」が行われることから「シヌグ堂」と呼ばれる御嶽があります 東(あがり)の御嶽とも言うそうです
東(あがり)の御嶽とも言うそうです 海が時化ることを祈るとは不思議な祭りだが、その昔、三山時代、戦いに敗れた南山の「平良忠臣」とその陣営が海を渡り、ここに身を隠したという謂われがあり、敵陣が海を渡れないように時化を祈ったことから始まっているそうです
海が時化ることを祈るとは不思議な祭りだが、その昔、三山時代、戦いに敗れた南山の「平良忠臣」とその陣営が海を渡り、ここに身を隠したという謂われがあり、敵陣が海を渡れないように時化を祈ったことから始まっているそうです 神々しい大きなガジュマルと祠があり、近くには自然石を利用した井泉「ハマガー」や、右手側にある階段を約10メートル登ると拝所もありました
神々しい大きなガジュマルと祠があり、近くには自然石を利用した井泉「ハマガー」や、右手側にある階段を約10メートル登ると拝所もありました
浜比嘉島、とても静かで穏やかな時間が流れている場所です
 楽しかったです~
楽しかったです~
Posted by aromama at 20:43│Comments(0)
│旅行